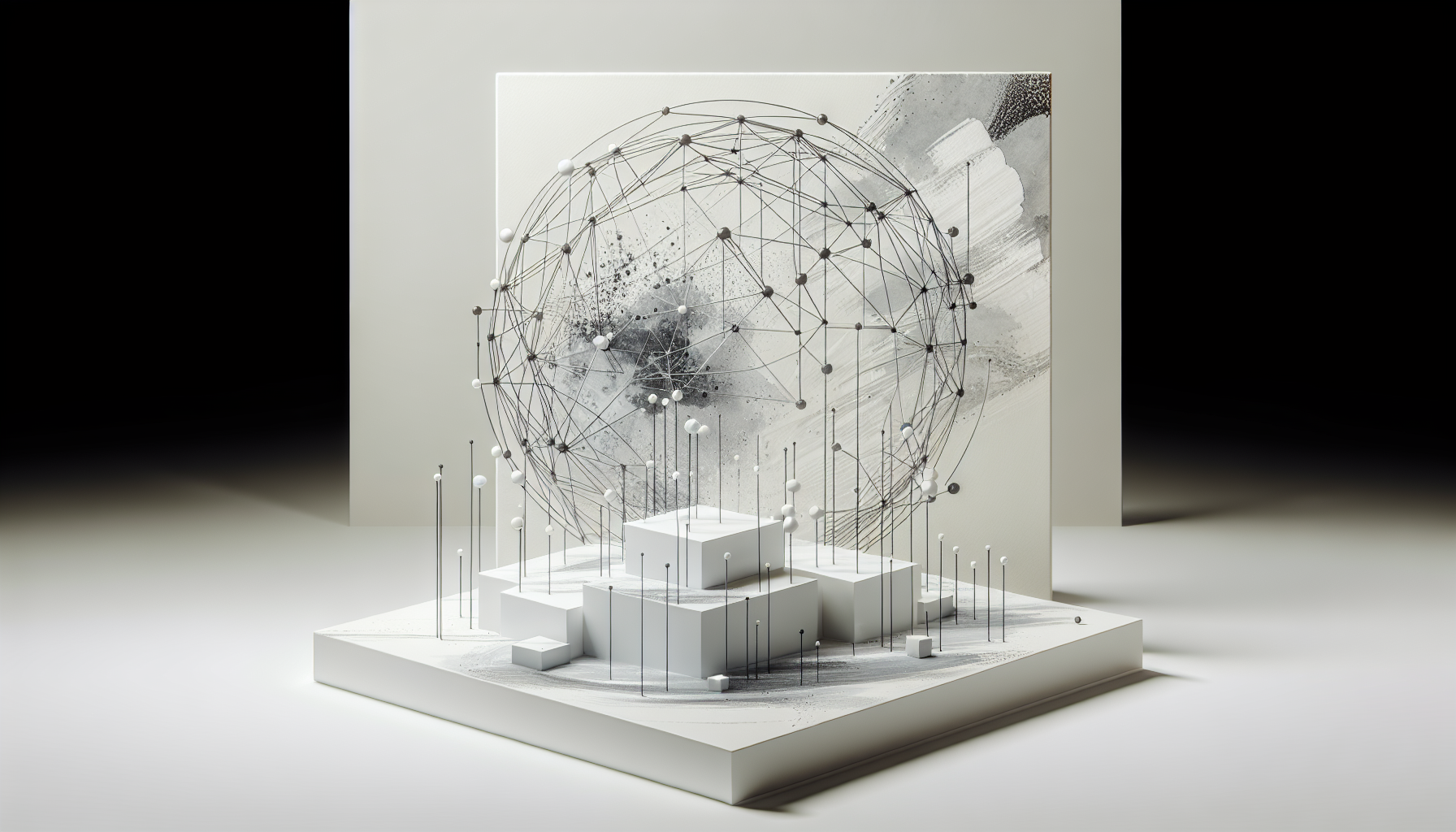AIが新卒採用を増やすという逆説
最近、ある経営者が「AIは新卒採用を増やす」と発言していた。
え?と思わないだろうか。世間では「AIが仕事を奪う」と言われているのに、なぜ真逆のことを言うのだろう。
どうやらこの経営者の頭の中では、AIのコストが下がることで、逆に人間の価値が際立つという構図があるようだ。AIが定型作業を大量に引き受けることで、人間は判断や責任、関係構築といった領域に特化する。だから新卒を採用して、そうした人間にしかできない仕事を担わせる必要があるのだと。
なるほど、一理あるかもしれない。でも本当にそんな単純な話だろうか。AIのコストが下がれば、むしろ人間を雇う理由そのものが問われるはずだ。そもそも会社という組織形態自体が、根本から変わってしまうかもしれない。
AIコストの急激な低下がもたらす変化
AIと人間のコスト差について、もう少し具体的に考えてみたい。現在、ChatGPTのAPIを使えば、100万トークン(約75万文字)の処理が数ドルで可能だ。これは、熟練した編集者が1週間かけて行う作業量に相当する。人件費に換算すれば、既に100倍以上の差がある。
しかも、この差は線形的ではなく指数関数的に拡大している。計算資源のコストは年々半減し、性能は倍増する。一方、人件費は社会保障費や教育コストを含めれば、むしろ上昇傾向にある。10年後には、この差が1万倍に達しても不思議ではない。
興味深いのは、この変化が生産性という概念そのものを無意味にしてしまうことだ。ある定義された作業の生産性を上げるといっても、それは計算資源を増やせばいくらでもスケールできる問題になってしまう。人間の価値は、もはやどれだけ速く処理できるかでは測れなくなるのだ。
では、このような時代に、なぜ企業は人を雇うのだろうか。それは、AIには担えない責任と判断、そして関係性が残るからだ。しかし、この前提も組織の形を大きく変えることになる。
消えゆく中間層と組織形態の三極分化
中小企業の多くは、規模の経済によって個人では難しい事業を可能にしている。しかし、AIによってこの前提が崩れつつある。
個人がAIを活用すれば、従来なら10人、20人で行っていた業務を一人でこなせるようになる。わざわざ中間的な規模の組織を維持する理由がなくなるのだ。これは悲観的な予測ではなく、技術的な必然性からの推論だ。
残るのは、以下の3つの形態だけだろう:
1. 大企業:高層ビルの建設、大規模インフラ、医薬品開発など、巨額の資本と物理的リソース、そして失敗時の大きな責任を負える存在としての大企業。これらは責任の引き受け手として残る。
2. 個人事業主:一人とAIの組み合わせで、従来の中小企業レベルの価値創造が可能に。法的責任も個人で完結し、身軽で柔軟な対応が可能だ。
3. ギルド型ネットワーク:プロジェクトごとに、専門性を持った個人が集まり、終われば解散する柔軟な協業形態。中世のギルドのような、横のつながりによる相互扶助と品質保証の仕組み。
この変化は、会社に就職するという20世紀型のキャリアモデルの終焉を意味する。代わりに、個人がAIとタッグを組み、必要に応じて他者と連携する、より流動的な働き方が主流になるだろう。
世代を超えた新しい分業と人間の役割
このような変化の中で、人間に残される役割も大きく変わる。そして興味深いことに、世代によって担う役割が分かれていく可能性がある。
若い世代の役割は、主にソフトウェア的な活動に集中するだろう。AIとの対話、新しいツールへの適応、デジタル空間での価値創造。彼らは資本を必要としない分野で、柔軟性と適応力を武器に活動する。SNSでの発信、オンラインでのサービス提供、バーチャル空間でのビジネスなど、物理的制約から自由な領域が主戦場となる。
一方、年配の世代は、長年の蓄積を活かした別の役割を担う。資本の調達と運用、物理的なビジネスの管理、リスクの引き受け。彼らの経験と信用は、AIには代替できない価値として残る。
面白いのは、この分業が対立ではなく補完関係を生む可能性があることだ。年配者が若手の視点や感性を必要とするとき、雇用ではなく人間側の接点として活用する。逆に若手は、年配者の資本と信用を借りて、より大きなプロジェクトに挑戦できる。
そして、すべての世代に共通して求められるのは、以下の3つの能力だろう:
- 構造設計能力:全体像を把握し、AIには見えない文脈を管理する力
- 責任引受能力:法的・倫理的な判断と責任を負う覚悟
- 関係構築能力:人と人をつなぎ、信頼を醸成する力
これらは、どれだけ技術が進歩しても、人間にしか担えない領域として残り続けるはずだ。
人間による対応がラグジュアリー化する時代
少し皮肉な現実について考えてみたい。AIのコストが下がり続ける一方で、人間による対応に特化した仕事のコストが相対的に非常に高くなってきている。
これは全ての人間の価値が上がるという話ではない。人間にしかできない特定の役割を担う人のコストが上昇しているのだ。高級ホテルのコンシェルジュ、一流レストランのソムリエ、プライベートバンカー。これらは既に人間による対応を付加価値としているが、この傾向があらゆる分野に広がっている。
人間が対応するサービスがプレミアムオプションとして課金される。それは、効率性とは真逆の、感情や共感、そして非効率だからこその価値を求める人間の本質的な欲求の表れかもしれない。
この変化は、私たちに根本的な問いを投げかける。効率と生産性を追求してきた近代社会の価値観は、どこへ向かうのか。人間の尊厳と価値は、何によって定義されるのか。そして、AIと共存する中で、私たちはどのような社会を築いていくべきなのか。
技術の進歩は不可逆的だ。しかし、その中でどのような選択をし、どのような社会を作るかは、まだ私たち人間の手の中にある。一人企業とAIの時代は、新しい可能性とともに、新しい責任をも私たちに突きつけている。