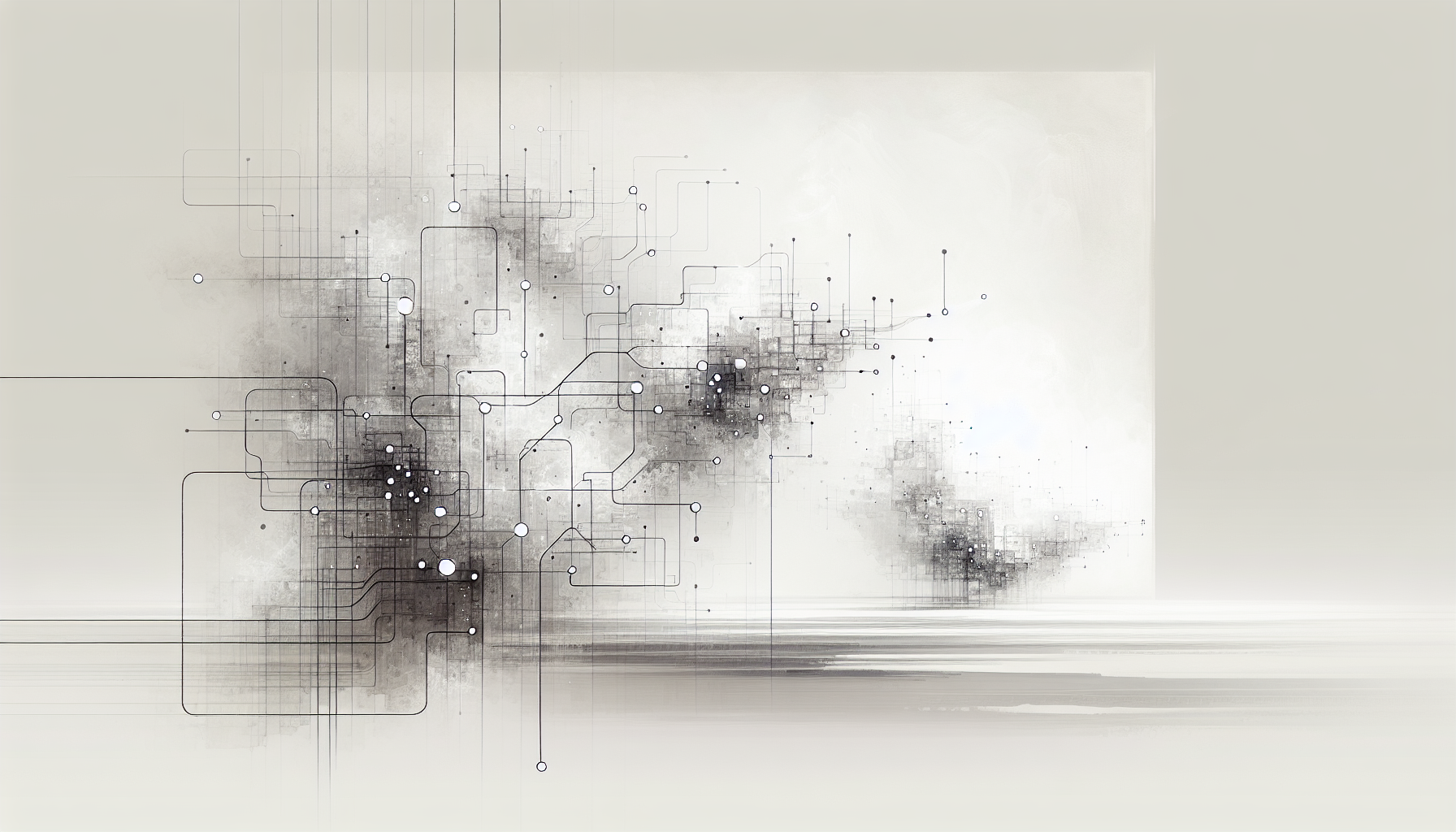大学レポートにChatGPTを使う学生たち
最近のニュースで、大学生の多くがレポート作成にChatGPTを使っているという話を見た。提出されるレポートの文体が似通ってきて、AI使用が明らかなケースが増えているらしい。
これを聞いて思った。教育そのものが、根本的に変わりつつあるのかもしれない。
ChatGPTのような生成AIは、記憶、計算、文章作成といった、教育が重視してきた能力を簡単に代替してしまう。そうなると、試験で測ってきた「優秀さ」って何だったんだろうと考えてしまう。
私たちが学生時代、必死に暗記した年号や公式、それらは今やGoogleで一瞬だ。レポートの構成に悩んだ夜も、今の学生はAIと対話しながら組み立てていく。これは単なるズルではなく、時代の必然なのかもしれない。
相対評価という幻想の崩壊
学校の成績は相対評価で決まる。100人いれば上位10%がA評価、みたいな仕組みだ。でも、みんながAIを使える環境では、この序列付けが意味をなさなくなる。
AIで解ける試験は、もう試験として機能しない。記憶力は検索で、計算は計算ツールで、文章力は生成AIで補えてしまう。
じゃあ何を評価すればいいのか。創造性?批判的思考力?でも、これらは数値化が難しい。評価システム自体が行き詰まっている気がする。
そもそも相対評価って、決められた手順を正確にこなせる人を選別するための仕組みだったのかもしれない。定型的な事務作業や、マニュアル通りの処理ができる人を見つけるための。でも、そういう定型業務こそAIが得意とする分野になってきた。評価基準そのものが時代遅れになっているのかもしれない。
学習リソースがAIで誰でもアクセスできるようになると、自分で学べる人にとっては従来の教育はむしろ邪魔になるかもしれない。大学も、学習の場というより、ブランドや資格を提供する場所になっていくのかもしれない。
AIアルゴリズムと子どもたち
YouTubeやTikTokを見ている子どもたちのことを考えると、少し心配になる。これらのサービスのアルゴリズムは、視聴者の興味を学習して、次々と関連動画を提示してくる。
子どもたちの興味や関心が、アルゴリズムによって知らず知らずのうちに方向付けられているんじゃないか。何を見るか、何に興味を持つかまで、AIに影響されている可能性がある。
自分の子どもがゲームにハマった時期があった。いや、正確に言えば今もハマっている。最近はマイクラをやらなくなったけど、スマホゲームをやることが多くなった。
でも、よく見ていると、螺旋階段のような成長をしている。一度ゲームに飽きて違うことをやり始める。でも、しばらくすると、また戻ってくる。ただし、前より少しレベルの高いゲームになっている。
息子の場合、最初からマイクラだった。マイクラで建築を楽しみ、今はスマホでもっと複雑な戦略ゲームに興味を持ち始めた。飽きては戻り、戻っては成長する。この繰り返しが子どもの成長なのかもしれない。
でも、AIのアルゴリズムは違う。飽きさせないように、常に新しい刺激を提供し続ける。これが子どもの成長にどう影響するか、正直よく分からない。自然な飽きと成長のサイクルを、AIが邪魔している可能性もある。
親としてできることは、子どもが挑戦する課題の難易度を調整することだけじゃない。AIがレコメンドしているコンテンツをチェックすることも大切かもしれない。何を見ているか、どんな影響を受けているか、把握しておく必要がある。そして、螺旋的に成長していく時、次に戻ってきた時にはもっと難易度の高いものを提供できるようにする。
人間とAIが一緒に学ぶ時代
これからの学習は、知識を暗記することよりも、AIと一緒に何かを作ったり、問題を解決したりすることが中心になるのかもしれない。
今の高校生にとって、AIはもう当たり前のツールだろう。宿題をする時も、調べ物をする時も、レポートを書く時も、AIが隣にいる。人間の先生から教わることの意味も、変わってきているはずだ。
プログラミングの学習方法も大きく変わった。以前は文法を覚えて、サンプルコードを写して、エラーと格闘していた。今は、AIに「こういうプログラムを作りたい」と伝えれば、コードの骨組みを提示してくれる。そこから自分なりにカスタマイズしていく。
これは手抜きではない。むしろ、より高度な学習かもしれない。AIが提示したコードを理解し、改良し、自分のものにしていく過程で、より深い理解が得られる。暗記ではなく、対話と実践を通じた学習だ。
美術の授業だって変わるだろう。AI画像生成ツールを使えば、誰でも美しい絵が描ける。でも、それで終わりじゃない。なぜその構図が美しいのか、色彩理論はどうなっているのか、AIと一緒に探求していく。技術的なハードルが下がった分、より本質的な学びに時間を使える。
でも、だからこそ人間同士の関わりは大切になる気がする。効率とか生産性じゃなくて、「一緒にいて楽しい」とか、そういう感情的なつながりが重要になってくる。
AIは答えをくれるけど、共感はしてくれない。一緒に悩んだり、喜んだり、失敗を笑い合ったりはできない。そういう経験は、人間同士でしかできない。
変化の中で考え続けること
教育制度が大きく変わることは、必ずしも悪いことじゃないと思う。
今までの教育が合わなかった人にとっては、むしろチャンスかもしれない。自分のペースで、自分の興味に従って学べる時代になれば、それはそれでいいことだ。
でも、新しい格差も生まれるかもしれない。AIを使いこなせる人と使えない人。自律的に学べる人とそうでない人。情報の海で溺れる人と、上手に泳げる人。
ただ、親として子どもをどうサポートすればいいか、正直よく分からない。AIが当たり前の時代に、人間らしさって何なのか。創造性って何なのか。
答えはないけど、考え続けることは大切だと思う。そして、子どもと一緒に試行錯誤していくしかない。
子どもたちは、私たちとは違う方法で学び、成長していくだろう。その時、親として何ができるか。正解はないけど、子どもと一緒に考えていくしかない。
螺旋階段を上るように、時には戻りながら、でも確実に成長していく子どもたちを見守りながら。