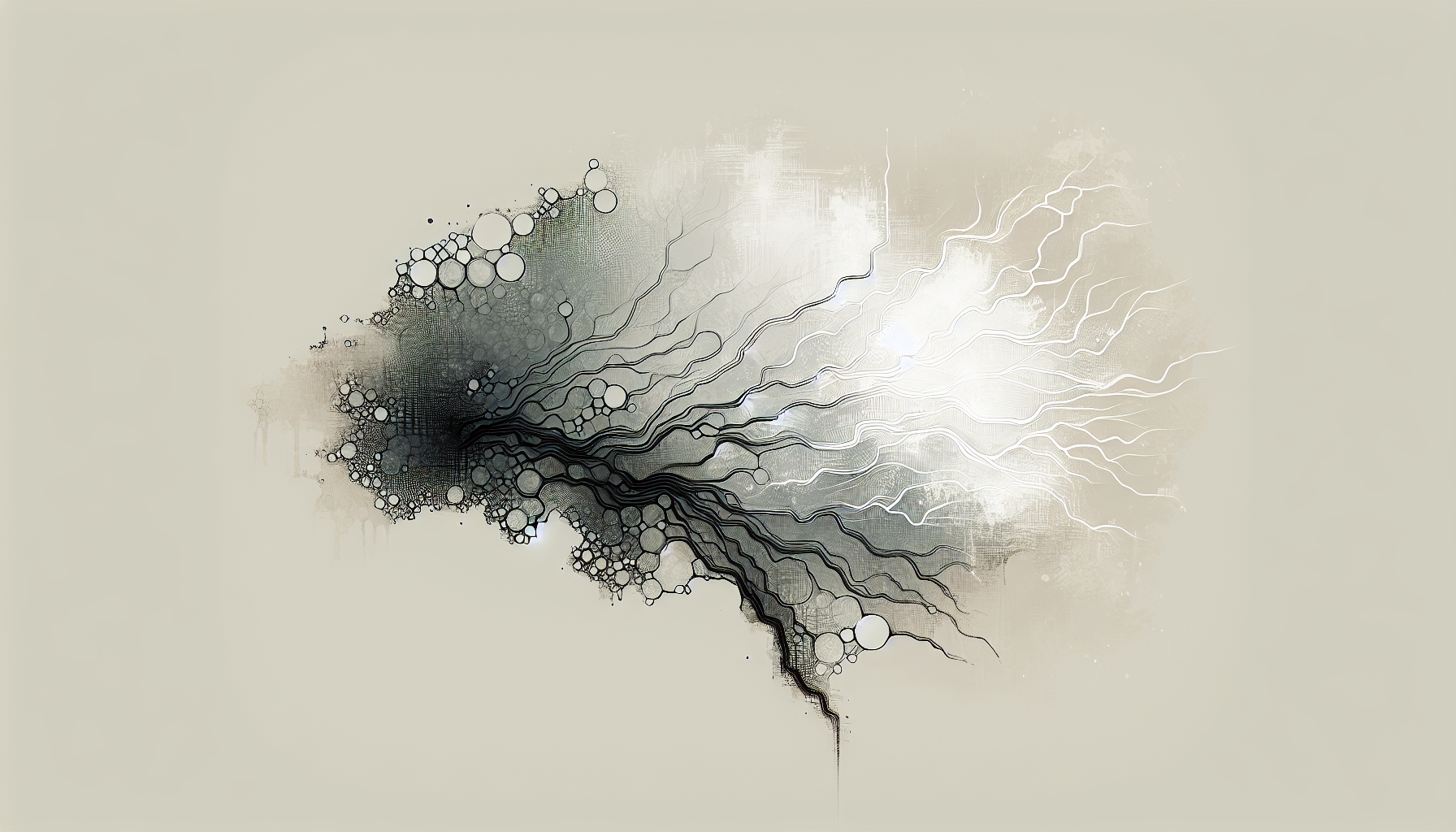長い間眠っていた想いの再起動
最近、私の中で長い間静かに眠っていたものが、ゆっくりと動き始めています。それは文章への想い、物語への憧れ、言葉で何かを表現したいという根源的な欲求でした。
若い頃から小説を読むのが好きで、自分でも物語を書いていました。文字に囲まれて生きていければ、それ以上に幸せなことはないと本気で思っていたのです。しかし20代の現実は厳しく、「文章では食っていけない」という冷たい事実の前に、私はその夢を諦めることになりました。
それから20年以上、IT系のエンジニアとして働いてきました。技術的な問題を解決し、システムを構築し、デジタルの世界で価値を生み出すことに専念してきたのです。その間も心の奥底では、いつか文章に戻りたいという想いがくすぶり続けていました。
AIという新しい可能性との出会い
ところが最近、状況が大きく変わってきました。AIが急速に進歩し、私たちの生活や仕事に現実的な影響を与えるようになったのです。特に文章生成の分野での進歩は目覚ましく、これまで人間だけができると思われていた創作的な作業にAIが参加できるようになりました。
これは私にとって、諦めていた道への扉が再び開かれたことを意味しています。もしかしたら、AIと協働することで、一人では実現できなかった文章の仕事が可能になるのではないでしょうか。技術者としての経験とAIの力を組み合わせれば、新しい形の創作活動ができるかもしれません。
この可能性に気づいた時、私の中で何かが確実に変わりました。長年封印してきた創作への情熱が、再び燃え上がり始めたのです。
一人とAIで挑む新しい働き方
私が目指しているのは、基本的に一人でできる仕事です。チームでの協働や人間関係の調整よりも、自分の思考とAIの能力を組み合わせて、何かを生み出すことに集中したいと考えています。
これは単なる人間嫌いということではありません。むしろ、人間とAIの協働という新しい働き方の可能性を探求したいのです。従来の仕事では多くの人が関わることで生まれる複雑さや制約がありましたが、AIとのパートナーシップなら、より純粋に創作に専念できるのではないでしょうか。
もちろん、これは実験的な試みです。本当に一人とAIで持続可能な仕事ができるのか、どのような価値を生み出せるのか、まだ分からないことばかりです。だからこそ、実際に試してみる必要があると感じています。
きそうしゃ – 実験の場として
そこで作ったのが、この「きそうしゃ」というサイトです。ここは私がAIと共に文章の世界で何ができるかを模索する実験場であり、思考を記録する場所でもあります。
「きそうしゃ」という名前には、「機械知能と共に稀なる想像を綴る」という想いを込めました。ありふれたものではなく、AIとの協働により稀有な文章を紡ぎ出す場所にしたいという意味です。ハブとなる場所を持つことで、散漫になりがちな思考や活動を一つの場所に集約できると考えています。
具体的に何をするかは、まだ完全には決まっていません。自分の考えを記録すること、実験の過程を文章にすること、そして文章を通じて何らかの価値を生み出すことを目指しています。古典文学の現代語訳から始まって、オリジナルのエッセイや分析記事まで、様々な可能性を探っていく予定です。
文章で生きるという古くて新しい挑戦
振り返ってみれば、私がやろうとしていることは決して新しいことではありません。文章で生計を立てるというのは、古くからある職業の一つです。しかし、AIという新しいパートナーを得ることで、この古典的な職業に新しい可能性が生まれているのではないでしょうか。
私の挑戦は、個人的な夢の実現であると同時に、AIとの協働による新しい働き方の実験でもあります。成功するかどうかは分かりませんが、少なくとも試してみる価値はあると信じています。
これからこのサイトで、私なりに文章と向き合っていこうと思います。AIと共に歩む文章の道がどこに続いているのか、私自身もまだ分からないのが正直なところです。しかし、その不確実性こそが、この挑戦を魅力的なものにしているのかもしれません。
私たちは今、技術と人間の創造性が新しい形で融合する時代を生きています。その中で、一人の人間とAIが協力して何を生み出せるのか。この問いへの答えを、実際の活動を通じて見つけていきたいと思っています。