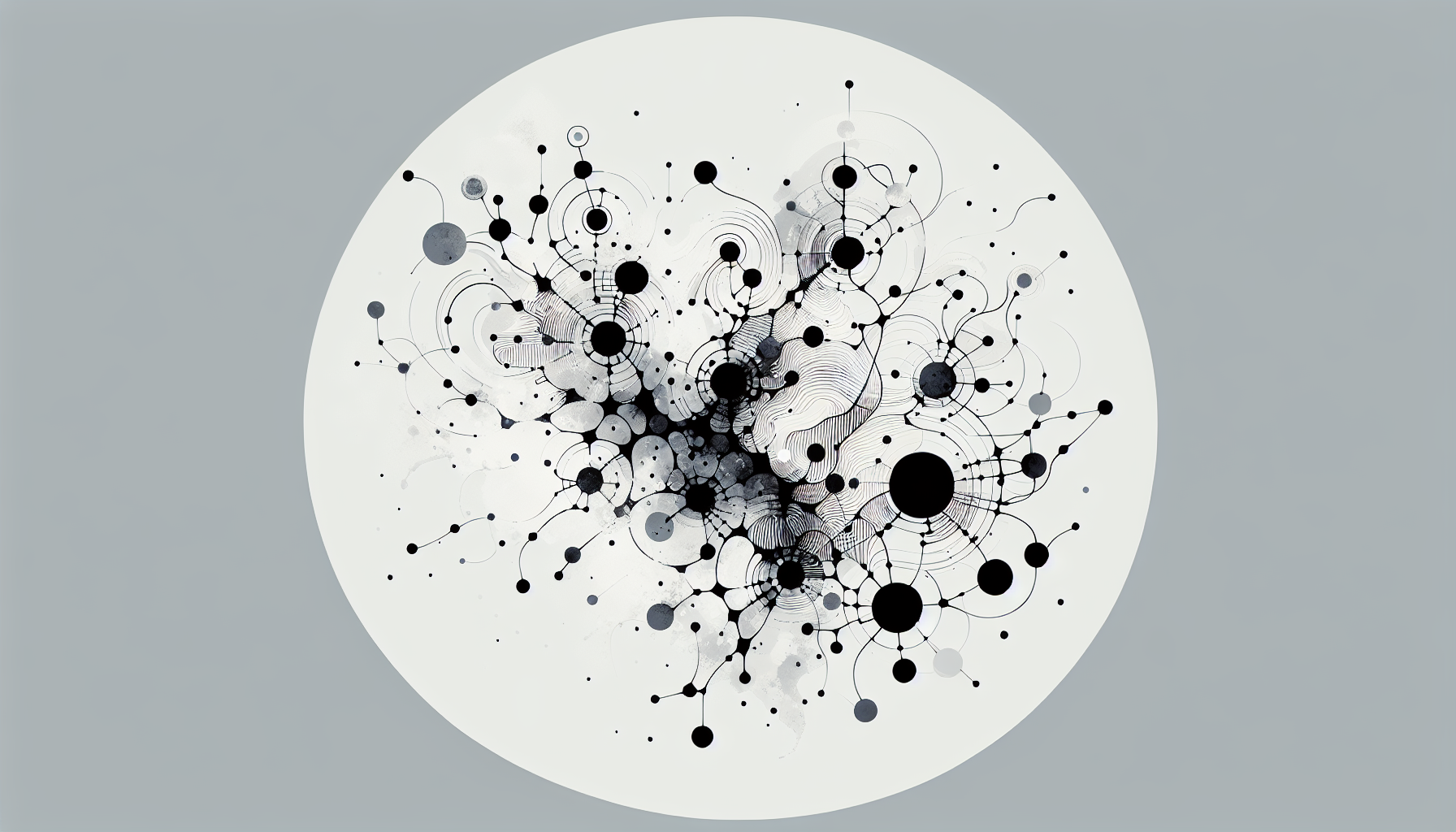理想から現実へ
以前、AIと共に文章の道を歩み始めた想いについて書きました。しかし理想を語るだけでは何も始まりません。実際にどのような環境を構築し、どのような方法でAIと協働しているのか。今回は、より具体的で実践的な話をしたいと思います。
私が現在取り組んでいるのは、コンテンツ創作のための「工房」とでも呼べる環境づくりです。物理的な工房ではなく、デジタル空間における思考と創作のためのシステムです。このシステムは、まだ実験の段階ですが、少しずつ形を成してきています。
Cursorエディターという中核
私のコンテンツ工房の中心に据えているのは、「Cursor」というエディターです。これは単なるテキストエディターではなく、AIとの協働に特化した開発ツールなのですが、コンテンツ創作にも非常に有効だと感じています。
なぜCursorを選んだのでしょうか。最大の理由は、思考の蓄積と整理に優れているからです。私の考えや断片的なアイデア、参考資料、作業中のテキストなど、コンテンツ創作に関わるあらゆるものを一つの場所に集約できます。そして、AIに対して的確な指示を出し、協働してテキストから様々な形式のコンテンツを作り上げていくことができるのです。
Cursorは私にとって、単なるツールではなく、思考のハブとして機能しています。ここで自分の考えを整理し、AIとの対話を重ね、様々な形式のコンテンツとして外部に発信していく。この一連の流れが、一つの環境で完結できることの価値は非常に大きいと感じています。
稀創舎との連携システム
Cursorで作成したコンテンツは、最終的にこのサイトで公開しています。この二つのプラットフォームを連携させることで、私なりのコンテンツ創作システムが形作られています。
Cursorは内向きの思考と創作の場であり、このサイトは外向きの発信の場です。この使い分けが重要だと考えています。Cursorでは遠慮なく実験的なテキストを書き、思考を深めることができます。一方、このサイトでは読者を意識した、より洗練されたコンテンツを提供する。この二段構えのシステムにより、創作の自由度と発信の質の両方を保てるのではないでしょうか。
また、技術的な面でも両者の連携を効率化しています。Cursorで作成したテキストを、適切な形式に変換してこのサイトに投稿するまでの流れを、可能な限り自動化しているのです。これにより、技術的な作業に時間を取られることなく、純粋にコンテンツ創作に集中できる環境を整えています。
重要なのは、私からのインプットはテキストという形でも、それが最終的に様々な形式のコンテンツに展開できることです。AIの強みの一つは、このマルチモーダル変換能力にあります。同じテキストから、記事として公開することもできれば、音声コンテンツに変換することも、動画の台本として活用することも可能です。これこそが、従来の「文章を書く」という作業を超えた、新しいコンテンツ創作の可能性だと考えています。
AIとの分担という現実的な選択
ここで重要なのは、私がAIとの関係をどう捉えているかということです。世間では「全自動化」や「AIが全てやってくれる」といった言葉をよく耳にしますが、現実はそう単純ではありません。特にコンテンツ創作においては、AIと人間の適切な分担が不可欠だと感じています。
現在のAIモデルの能力は確かに優れていますが、限界もあります。特に日本語における表現の微妙なニュアンスや、個性的な文体の再現には、まだ課題があると感じています。完璧な日本語を期待するとがっかりすることも多く、どうしても偏りが出たり、不自然な表現が生まれたりしてしまいます。
しかし、この限界を否定的に捉える必要はないと考えています。むしろ、人間が関与する余地があるからこそ、オリジナリティや個性が生まれるのではないでしょうか。AIが作る「完璧」で「標準的」なコンテンツに対して、人間が加える「不完全さ」こそが、個性という形で価値を持つのです。
オリジナリティを守るための戦略
これからの時代、AIがコンテンツの良し悪しの基準を決めるようになる可能性があります。そうなった時、その基準から意図的に外れることが、個性や独創性の表現になるのかもしれません。これは決して新しい発想ではなく、芸術や文学の世界では古くから見られる現象です。
私がAIとの協働において重視しているのは、アイデンティティの維持です。全てをAIに任せてしまえば、確かに効率的かもしれません。しかし、それでは創作者としての私の価値が失われてしまうのではないでしょうか。ネット上で個としての存在感を保ち続けるためには、人間がある程度の割合で関与し続けることが必要だと考えています。
具体的には、AIが生成したコンテンツを必ず自分でチェックし、自分の文体や思考に合うように調整しています。時には大幅に書き直すこともありますし、AIの提案を完全に却下することもあります。この過程こそが、私の個性をコンテンツに込める重要な作業だと考えています。
共創という新しい関係性
ここで誤解していただきたくないのは、私がAIを単なる道具として使っているわけではないということです。AIとの関係は、むしろ「共創」と呼ぶべきものだと感じています。AIには私にはない発想力や情報処理能力があり、私にはAIにはない感性や価値観があります。
この違いを活かし合うことで、一人では生み出せなかったコンテンツが生まれる可能性があります。重要なのは、どちらか一方が主導権を握るのではなく、互いの特性を理解し、尊重し合うことです。私はAIから学び、AIは私から学ぶ。そのような相互作用の中で、新しいコンテンツ表現が生まれてくるのではないでしょうか。
まだ始まったばかりの実験
この取り組みはまだ始まったばかりです。本当にこの方法で持続可能な創作活動ができるのか、どのような価値を生み出せるのか、確信があるわけではありません。技術的な課題もありますし、創作面での課題もあります。
しかし、だからこそ今この実験を続ける価値があると考えています。AIとの協働によるコンテンツ創作という新しい領域は、まだ誰も正解を知らない未知の分野です。試行錯誤を重ねながら、自分なりの方法論を築いていく過程そのものが、貴重な経験となるはずです。
私が目指しているのは、単なる効率化ではありません。人間とAIが協力することで生まれる、新しい形の創造性を探求したいのです。その過程で、テキストから始まって音声、動画、さらには私たちがまだ想像できないような形式のコンテンツまで、表現メディアの新しい可能性を発見できるかもしれません。
今後も、この実験を継続し、その経過を時折このサイトで報告していければと思います。成功も失敗も含めて、AIとの協働によるマルチモーダルなコンテンツ創作という挑戦について、気が向いた時に記録していこうと考えています。私たちが生きているこの時代の可能性を、実際の行動を通じて探っていきたいと思っています。