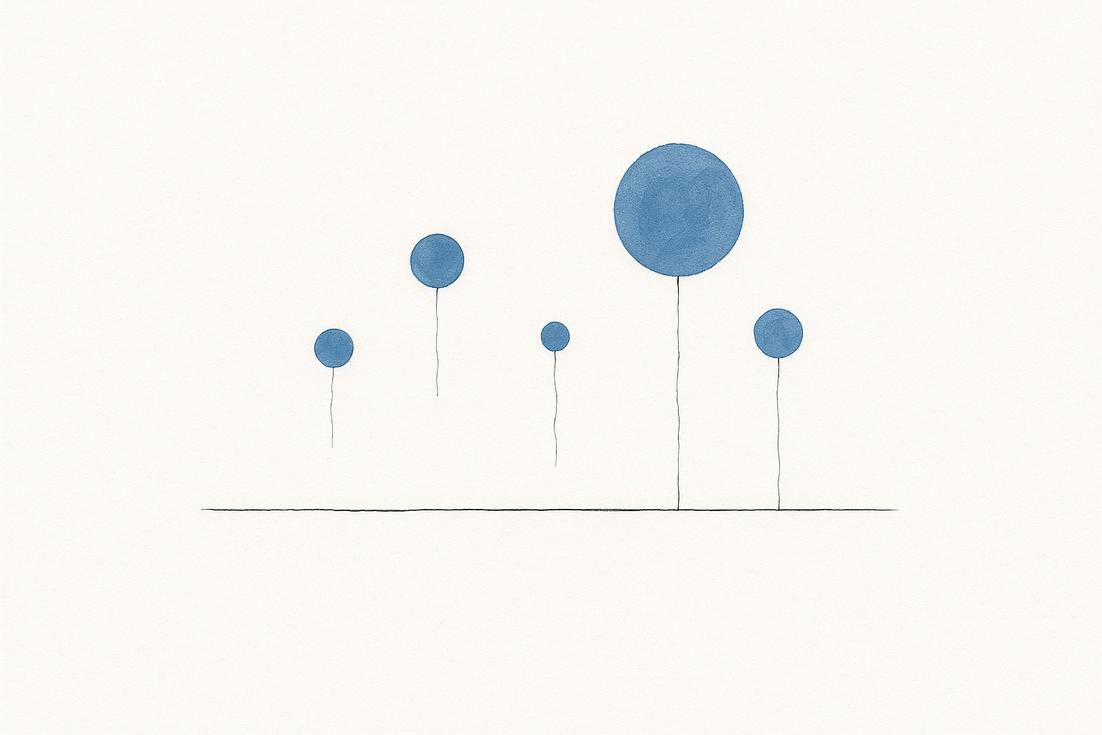AIの将来について考える時、私たちは往々にして表面的な現象に目を奪われがちです。しかし、現在のAIブームの構造を冷静に分析してみると、興味深い二極化が見えてきます。
1%と99%の構造
現在のAIビジネスは、大きく二つに分類できると私は考えています。一つは、AIモデルそのものを開発しているベース側のビジネス。もう一つは、既存のモデルをラップして二次利用的なサービスを提供している側です。
数として見れば、99%は後者のラップ系ビジネスでしょう。ChatGPTやClaude、Geminiといった既存モデルの上に独自のUI を作り、特定の用途向けにプロンプトを最適化してサービス化する。これが現在のAIビジネスの大半を占めています。
しかし、この99%のビジネスには構造的な問題があります。本質的には「UIの提供」と「プロンプトの最適化」に過ぎないからです。
プロンプトエンジニアリングの黄昏
GPT-4が登場した頃、プロンプトエンジニアという職種が非常に注目されました。高額な報酬でプロンプトエンジニアを募集する企業も珍しくありませんでした。
ところが最近では、そうした求人をほとんど見かけなくなっています。なぜでしょうか。
答えは単純です。AIモデル自体の読解力が飛躍的に向上したからです。以前なら「あなたは天才ライターです」といった詳細な役割設定や、複雑な指示が必要だった作業も、今では「このニュースについて書いて」と言うだけで、適切な記事を生成してくれます。
AIの能力向上により、プロンプトの重要性は相対的に低下しました。UIについても、将来的にはAI自体がユーザーのニーズに合わせてダイナミックに生成できるようになるでしょう。
こうした技術的進歩を考えると、現在わらわらと湧いている99%のラップ系AIビジネスは、遠からず淘汰されていくと予想されます。
AGIは構造デザイナーとして進化する
では、AI技術の進歩の先には何があるのでしょうか。AGI(汎用人工知能)の登場がよく話題になりますが、私はこれが一般的に想像されているような「何でもできる万能AI」にはならないと考えています。
むしろAGIは、様々な専門的なエージェントを統括し、全体の構造を把握して適切な指示を出す「構造デザイナー」のような存在になるのではないでしょうか。
現在の人間のマネージャーが行っているような業務です。全体の状況を俯瞰し、どのタスクをどのエージェント(AIまたは人間)に振り分けるべきかを判断する。外部環境の変化に応じて、ワークフロー全体を最適化していく。そんな役割を担うAIがAGIと呼ばれるようになると思います。
数値化できるものとできないもの
ここで興味深い問題が浮かび上がります。AGI構造デザイナーが最適化できるのは、基本的に計量可能な指標に限られるということです。
売上、効率性、完了時間。こうした数値で表現できる要素については、AIは人間を遥かに凌ぐ最適化を実現するでしょう。しかし、人間の「幸福」という計量困難な要素はどうでしょうか。
年収や健康状態といった間接指標を使えば、データ上は幸福を扱うことも不可能ではありません。しかし、データ上の幸福と個人が実際に感じる幸福は、必ずしも一致しません。年収が高くても不幸な人もいれば、健康であっても満足していない人もいます。
この「数値による最適化」と「体感的満足」のギャップは、AGI時代の重要な課題になると考えられます。
新しい役割分担の誕生
結局のところ、AGIの制約は性能的な限界というより、根本的な性質の違いです。幸福を感じることができないものに、幸福を基準とした判断を求めるのは無理があります。
そこで生まれるのが、新しい役割分担です。AGIは計量可能な要素の最適化に特化し、人間は「何を最優先の価値とするか」「どんな制約条件を設定するか」といった価値判断を担う。
例えば、「離職率を一定以下に保つという制約の中で、生産性を最大化せよ」という形で、人間が価値基準を設定し、AIがその条件下での最適解を導き出す。こうした協働関係が、AGI時代の標準的な働き方になるかもしれません。
インフラ化するAI
現在のAIバブルは確実に存在しますが、それは99%のラップ系ビジネスの話です。1%のモデル開発側は、社会インフラとして確実に定着し、長期的なビジネスとして成長していくでしょう。
重要なのは、この変化の本質を見極めることです。表面的な技術の応用に一喜一憂するのではなく、社会構造そのものがどう変化していくかを考える必要があります。
私たちはどう対応すべきか
では、この大きな変化の中で、私たちはどう向き合えばよいでしょうか。
まず大切なのは、「複雑で価値の高い問題」を見つける目利き力を養うことかもしれません。AGI時代において人間の競争優位は、高性能なAIを使えることではなく、そのAIでなければ解けない本質的な問題を発見することにあるからです。
そして、AIによる効率化の恩恵を受けながらも、人間らしい価値判断を大切にしていく。AIに任せるべきことと、人間が担うべきことの境界線を、常に意識していく必要があるでしょう。
技術の進歩は止まりません。しかし、その進歩の中で私たち人間が果たすべき役割も、確実に存在し続けるのです。